
心に残る学会内容


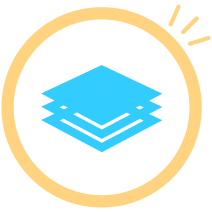
心に残る学会内容

ホーム
院長ご挨拶
心に残る学会内容
心に残る学会内容詳細
眼科手術における重篤な合併症の1つである術後感染性眼内炎は、発症がまれなために蓄積されたデータこそ少ないが、現在、医療訴訟の大きな問題となっており、対策が急務とされている。
先ごろ神戸市で開催された第52回日本臨床眼科学会(会長=神戸大学眼科・山本節教授)ではシンポジウムに「術後感染症の予防と処置」(オーガナイザー=昭和大学病院眼科・小出良平教授)が取り上げられ、4人の演者が(1)白内障(2)緑内障(3)網膜・硝子体(4)外眼部の手術における術後感染症の危険性について、これまでに集められたデータを元に、それぞれの視点から検討を重ねた。
目次
~白内障手術~ 術後眼内炎防止に嚢内洗浄が有用
白内障手術後の重篤な合併症の1つである術後眼内炎は、発症頻度こそ0.1%弱とまれなものの、予後が不良であることが指摘されている。とつか眼科(名古屋市)の戸塚伸吉院長(昭和大学兼任講師)は同大学関連施設のこれまでのデータを示し、大量の眼内灌流液による水晶体嚢内洗浄の有用性を指摘した。
多くは術後1か月以内の急発
同院長はまず、過去5年間に同大学関連30施設で白内障手術後に眼内炎を発症した33例(発症率0.074%)について報告。それによると、発症日は手術翌日から395日後にまでわたるが、多くは術後1か月以内の急性発症だった。患者の主訴は視力低下、疼痛、充血などで、同定できた起炎菌は表皮ブドウ球菌や黄色ブドウ球菌など結膜嚢常在菌が多いが、多剤耐性菌も増加していた。患者には薬物療法、嚢内洗浄、硝子体切除および眼内レンズ摘出などの処置を施しており、処置後は3分の1が予後良好であった反面、糖尿病と脳梗塞を基礎疾患に持つ2例が失明した。
術前無菌法と結膜嚢常在菌について滅菌綿棒を用いた細菌培養検査を白内障手術患者203例に実施し、細菌検出率を見たところ、術前の抗菌薬の点眼によっても完全な無菌化には至らず、抗菌薬点眼の予防投与は絶対的に有用ではない可能性が示唆された。また、結膜嚢洗浄操作には必ずしも消毒剤を用いる必要性はないとの結論を得た。
一方、術後の前房蓄膿に対しては眼内レンズの摘出や抗菌薬の前房内注入、硝子体注射を行わずに大量の眼内灌流液で水晶体嚢内を洗浄する方法を7例に施行して良好な結果を得ており、同院長は「手技が容易な嚢内洗浄は有用な治療法の1つであり、細菌性眼内炎と分かったら直ちに施行してもよいと考えている」と述べた。この知見はシンポジウム後半のディスカッションにおいても大きな関心を集め、他の演者から「薬物療法施行後の嚢内洗浄実施例であることから、嚢内洗浄そのものの効果を確かめることが必要」とのアドバイスが寄せられたほか、洗浄時間や灌流液の使用量についての質問に対して同院長は「洗浄時間についてははっきりしたことは言えないが、100ml以上の灌流液を使っている」と答えた。
生食液洗浄で付着菌減少
同院長らはまた、眼内レンズの細菌付着性についても検討。「静電気など物理化学的な力と細菌が持つ粘着力の2つに分けて対策を講じなければならない」との考えのもとに,表皮ブドウ球菌を用いて眼内レンズの細菌付着を定量化する実験の結果、物理化学的な付着力は不明だったものの、(1)アクリルソフトレンズ(2)ツーホールPMMAワンピースレンズおよびノーホールPMMAワンピースレンズ(3)ヘパリングレンズの順に細菌が付着しやすいことが分かり、生食液による機械的洗浄で付着細菌が減少する可能性がある、と述べた。
~緑内障に対する線維柱帯切除術~ MMC併用時には濾過胞の形態に注意
東京大学眼科の鈴木康之講師は、緑内障に対する線維柱帯切除術後に遅発性感染症が発症する恐れがあるため、濾過胞の形態に注意する必要がある、と報告した。
血管に乏しく感染の危険性高い
緑内障に対する降圧術として最も有効な術式と考えられている線維柱帯切除術は、代謝拮抗薬のフルオロウラシルおよび抗生物質のマイトマイシンC(MMC)の併用によって効果を上げ、わが国に多い正常眼圧緑内障への有効性が報告されている。しかし、同手術によって形成される濾胞壁の多くは薄く、血管に乏しいため感染の危険性が高い。感染は前房内に広がって眼内炎を惹起するばかりか、硝子体まで達した場合、視力予後に大きな影響を及ぼす。
鈴木講師は、同手術における遅発性感染症の頻度を「最近10年間に施行した約1,600例のうち、フルオロウラシル使用714例中12例(1.7%)、MMC使用963例中6例(0.6%)の計18例に遅発性感染症を確認した」と報告し、欧米のデータの検討を加えて「同手術施行後には症例の2%程度というかなり高率な割合で遅発感染が起きる可能性がある」と警告した。
同講師らが薬剤別に調べたところ、MMC併用の約8割に薄く、血管の少ない濾過胞が見られることが分かった。また、このような濾過胞ではSeidel試験によって、濾過胞から房水の漏出またはしみ出しが高率に生じており、非常に感染しやすいことが判明。「MMC併用線維柱帯切除術後の経過観察においては濾過胞の形態に十分に注意し、感染の早期発見に努めてほしい」と述べた。
~硝子体手術~ 術後眼内炎発症例の視力予後は不良
福岡大学眼科の松井孝明講師は、硝子体手術後の感染性眼内炎の自験例とアンケート調査結果から、発症例の視力予後は不良だとして、感染性眼内炎への対策と処置について報告した。
施設により発症頻度に大きな差
白内障および眼内レンズ手術後の眼内炎については多くの報告があるが、硝子体手術後の眼内炎については調査例も多くなく、発症頻度や特徴などは明らかになっていない。米国の研究では発症頻度は0.05~0.07%で術後早期に発症し、一般に視力予後が不良であるとされている。
松井講師によると、同科で行った硝子体手術4,727例の術後に3例(0.06%)の感染性眼内炎が発症したという。
また、全国の眼科治療施設114施設から回収したにアンケートを集計したところ、31施設が45例の硝子体手術後の眼内炎を経験していた(平均発症頻度は8万3,596例中45例、0.054%)。原疾患は増殖糖尿病網膜症(14例)、網膜上膜形成症(11例)、網膜静脈分岐閉塞症(5例)、特発性黄斑円孔(3例)など。施設別では124例中に2例発症したものから、9,000例の手術を施行してもいまだ1例も発症していないものまで発症頻度は大きく分かれる。
多くは術後3日以内に発症しており、検出できた起炎菌はコアグラーゼ陰性ブドウ球菌と緑膿菌がそれぞれ4例、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)が2例、大腸菌が2例などでグラム陽性菌が多かった。患者の視力予後は0.1以上に回復したものが19例だった反面、0.01未満が22例と半数近くを占め、米国の報告と同様に予後不良であることが示された。
何よりも予防が先決
一方、予防策としては「術野の消毒」「術野の洗浄」「ドレーピング」「術前後の抗生剤注入」「睫毛カット」などが一般的に講じられていたほか、「結膜切開 を小さくする」「closedeyesurgeryに徹する」「硝子体はできる限り切除する」「涙嚢洗浄」「術後診察を頻繁に行う」を挙げた施設もあり、同講師はこれらの回答を検討して「感染性眼内炎は手術侵襲による炎症と鑑別が困難な場合があるが、何よりも予防が先決で、術野の無菌化と器具の滅菌を徹底することが重要。また、万一発症した 場合は硝子体手術で病巣を除去し、抗菌薬灌流を行うことが有効と思われる」と結んだ。
~外眼部手術~ 局所感染や炎症のある例では十分な注意を
同院長はまず、過去5年間に同大学関連30施設で白内障手術後に眼内炎を発症した33例(発症率0.074%)について報告。それによると、発症日は手術翌日から395日後にまでわたるが、多くは術後1か月以内の急性発症だった。患者の主訴は視力低下、疼痛、充血などで、同定できた起炎菌は表皮ブドウ球菌や黄色ブドウ球菌など結膜嚢常在菌が多いが、多剤耐性菌も増加していた。患者には薬物療法、嚢内洗浄、硝子体切除および眼内レンズ摘出などの処置を施しており、処置後は3分の1が予後良好であった反面、糖尿病と脳梗塞を基礎疾患に持つ2例が失明した。
術前無菌法と結膜嚢常在菌について滅菌綿棒を用いた細菌培養検査を白内障手術患者203例に実施し、細菌検出率を見たところ、術前の抗菌薬の点眼によっても完全な無菌化には至らず、抗菌薬点眼の予防投与は絶対的に有用ではない可能性が示唆された。また、結膜嚢洗浄操作には必ずしも消毒剤を用いる必要性はないとの結論を得た。
一方、術後の前房蓄膿に対しては眼内レンズの摘出や抗菌薬の前房内注入、硝子体注射を行わずに大量の眼内灌流液で水晶体嚢内を洗浄する方法を7例に施行して良好な結果を得ており、同院長は「手技が容易な嚢内洗浄は有用な治療法の1つであり、細菌性眼内炎と分かったら直ちに施行してもよいと考えている」と述べた。この知見はシンポジウム後半のディスカッションにおいても大きな関心を集め、他の演者から「薬物療法施行後の嚢内洗浄実施例であることから、嚢内洗浄そのものの効果を確かめることが必要」とのアドバイスが寄せられたほか、洗浄時間や灌流液の使用量についての質問に対して同院長は「洗浄時間についてははっきりしたことは言えないが、100ml以上の灌流液を使っている」と答えた。
術後感染の危険性は激減
同科長は「優れた消毒剤や抗菌薬の登場によって術後感染を起こす危険性は激減し、万一、感染を起こしても血行が良好な眼瞼などでは薬剤の移行が良好なため、免疫反応に問題がなければ大事に至ることは比較的まれ」としながらも、「涙道や眼窩の手術では患者の状態に加えて、術前の消毒や術中の操作によっては重篤な術後感染を来すことがある」ことを強調した。
同科長はまた、(1)先天性鼻涙閉塞開放術や涙管シリコンチューブ挿入術などでは、盲目的操作によって鼻涙管外に穿孔して感染を周囲に広げる危険性がある(2)網膜復位術や義眼台充填術、眼窩底骨折手術などでは縫合糸や手術の際に留置するシリコンやヒドロキシアパタイトなどの異物の周囲に膿瘍を形成することがある、と述べた。そのため、同科長は「糖尿病や膠原病、喘息、アトピー性皮膚炎などによるステロイドの連用は患者の全身免疫力の低下を来し、感染しやすい状態となる。局所感染や炎症のある症例の手術に関しては十分な注意が必要」と訴えた。